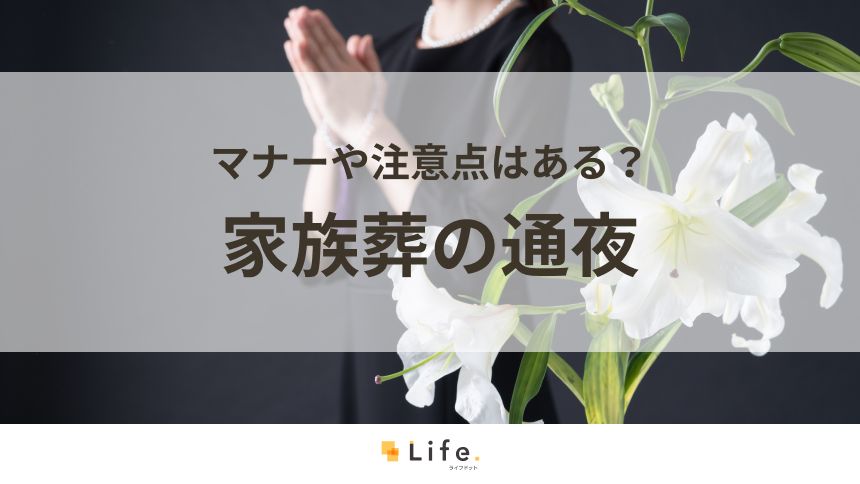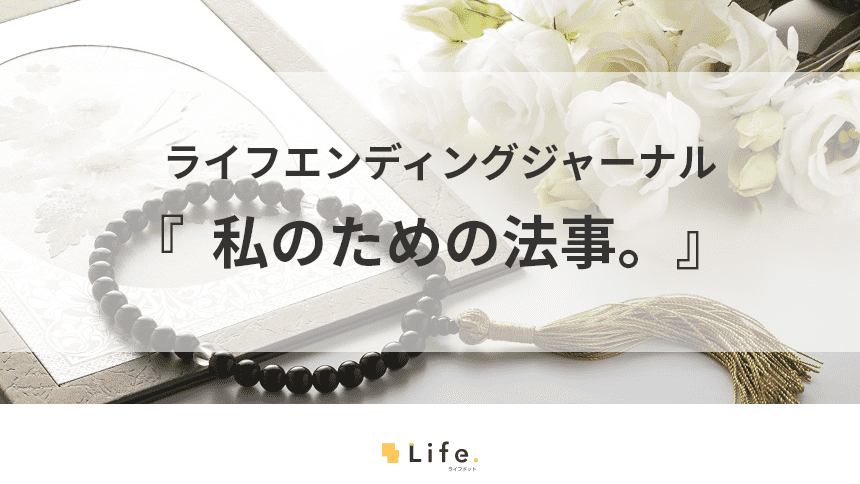エンバーミングとはどんなもの?ご遺体を修復・保存する特殊技術について
人は、命を引き取ると生前とは違う姿へと少しずつ変わっていきます。日本では「火葬」の文化があるため、亡くなった人はかなり早めに火葬に処されることになります。
しかし、何らかの事情で、火葬をするまでの時間が伸びたり、またご遺体の状態によってはそのままの姿で送るのは忍びない……とご家族が思われたりすることもあります。
そんなときに出てくるのが、「エンバーミング」という考え方です
ライフドット推奨
後悔しないお墓のために今から準備してみませんか?
終活といっても、生前整理、葬儀、お墓の検討などさまざまです。
そのなかでも「お墓」は、一生に一度あるかないかの買い物ですね。
- 自分のライフスタイルに合ったベストなお墓はどういうものなのか知りたい
- お墓選びで複雑な手順を簡単に詳しく理解したい
- お墓選びで注意するべきポイントを詳しく知りたい
など、数々の不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。
お墓の購入に関しては、初めての方が多いため、不安や疑問を持つことは仕方のないことでしょう。
しかし、お墓購入後に後悔することだけは避けたいですよね。
そのためにも複数の霊園・墓地を訪問して実際に話を聞き、しっかりと情報収集することをオススメします。
情報収集するために、まずは気になる霊園・墓地の資料請求をしてみましょう。
ライフドット編集部おすすめ記事
この記事の目次
エンバーミングとは
「エンバーミング」は「embalming」と書きます。これはなかなか日本語に直訳しにくい言葉であり、また日本においては「根付いている」とはいえない文化でもあります。
エンバーミングは、簡単にいえば、「亡くなった人の姿をとどめておくための技術」のことです。生命を失った生き物は、そのままの状態にしておけばやがて傷み、腐っていきます。
しかしエンバーミングを施すことによって、その体はまるで生きているときのような姿を長くとどめておくことができるようになります。
ちなみに、エンバーミングを施した場合、約2週間程度はご遺体の保存ができます。
このため、「海外に行っている家族が戻ってくるまで、遺体を保存しておいてほしい」などのような希望も叶えることができます。
加えて、エンバーミングの場合はドライアイスも必要としないため、「冷え切ったご遺体」ではなく、生きていたときのような体のままで対面ができるというメリットもあります。
エンバーミングにおける最初の段階として、「ご遺体を消毒する」というものがあります。
ご遺体を消毒し、殺菌をし、腐敗を防ぐための準備をします。また、血液を抜いたり防腐剤を入れたりすることで、ご遺体が変わっていくことを防ぎます。
これによって、故人を生前の状態にとどめておきやすくなるだけでなく、腐臭や死臭を軽減することも可能です。
「どこまでをエンバーミングとするか」は、人によって解釈が異なるかもしれません。
ただ、エンバーミングは多くの場合、「ご遺体の修復」を含むと考えられる場合が多いと思われます。これを行う人は、特に「(ご)遺体修復師」「復元師」などの名前で呼ばれることもあります。
長患いをしているうちに、頬がこけてやせ細ったり、眼窩が落ち込んだりすることがあります。エンバーミングではそれらも丁寧に修復し、在りし日の姿に近づけます。
特に「修復」という技術が重要視されるのは交通事故などで亡くなった人の場合です。ご遺体の損傷が激しくご家族がひどいショックを受けると考えられた場合、エンバーミングが依頼される場合もあります。
もちろん、「エンバーミングを頼めば絶対に元通りになる」「従来の包帯で覆うかたちの処理は、良くない」などのように言い切ることはできません。
しかしながら、「できるだけ生前の姿で送りたい」「闘病生活は過酷で、顔も面変わりした。だからこそ、最後にお別れするときは、元気だったときの姿で見送りたい」「兄は交通事故で亡くなった。損傷の激しい兄の遺体を見たら、母は強いショックを受けるだろう」という考え方から、エンバーミングを頼む人は少なくありません。
なお、エンバーミングの場合は、防腐作業やご遺体の修復作業を行った後、死に化粧などを施すのが一般的です。
このため、エンバーミングを依頼した際は、別途で死に化粧などを頼む必要はほとんどありません。もっとも、念のために「どこまでやってくれるのか」「死に化粧もプランに含まれるのか」などは確認しておいた方がよいでしょう。
また、「どこに頼めばよいかわからない」という場合は、とりあえず葬儀会社に相談してみてください。
エンバーミングの歴史
この「エンバーミング」に近い考え方は、すでに古代エジプトの頃にまでさかのぼることができるといわれています。
もっとも、現在のようなかたち・考え方を取るようになったのは、1861年~1865年に掛けて起きたアメリカの南北戦争がきっかけであったといわれています。
多数の死者が出るなかで、亡くなった兵士を家族の元に送り届けるための技術としてエンバーミングが研究されました。
また、このエンバーミングの技術は、各代の大統領などのご遺体を保存するためにも使われています。
しかし、日本においてはこのエンバーミングの考え方はそれほど広まりませんでした。なぜなら日本には「火葬」といった方法があるからです。
日本では特例を除き、そのままの状態でご遺体を眠らせることはできず、必ず一度火葬してお骨にしなければならないという決まりがあります。
火葬までにかかる時間は、地方や葬儀会社と火葬場の空き状況、あるいは宗教者(たとえば僧侶など)やご家族のスケジュールにもよりますが、最大でも10日程度です。
多くのケースでは1週間以内に火葬されますし、地方ならば「ご逝去から4日目以降にならないと火葬できなかったという経験は、葬儀会社に勤めていた数年の間で一度もない」と語る葬儀会社の社員もいました。
土葬が基本となる海外とは異なり、ご遺体が傷む前に火葬に附すことになる日本において、エンバーミングという考え方・エンバーミングという技術が根付かなかったことは、ある意味当然だといえるでしょう。
そのため、日本にエンバーミングの考え方が入ってきたのは非常に遅く、南北戦争から100年以上も後、1980年代の後半になってからです。
現在は日本でもこのエンバーミングを取り扱う学校も出てきていますから、少しずつ浸透していったといえるでしょう。
「日本に浸透していったエンバーミング」で特に取り上げるべきなのは、2011年の3月11日の東日本大震災の悲劇です。
未曾有の被害を出したこの大震災は今でも記憶に新しいものですが、この痛ましい災害時に「ご家族と故人の別れが、せめて少しでも安らかなものであるように」との願いの元、活躍したエンバーマー(エンバーミングを行う人)の方々がいました。
ご遺体から泥を取りのぞき、ご遺体をできるかぎり整えたといわれています。
この頃には防腐処理に必要なドライアイスなどの数が足りずエンバーミングに求められる「防腐処理」を行うことは難しかったと言われていますが、エンバーミングの考え方の基本である「お別れのときを、少しでも安らかに」という理念はしっかりと反映されていたといえるでしょう。
また、公衆衛生上の都合から、火葬場が十分に動かせない状況のなかでどうしても仮埋葬を行わなければならなかった自治体もあります。仮埋葬を終えた後火葬場が動かせるようになった後にご遺体を再度出して火葬に処したところもあったとされています。
ただ、これは、どちらが良かった・悪かったと語られるべきものではありません。どのような状況であっても、人の生命に敬意を表し、できるだけのことをしたい……と考えた多くの人によって行われたことだからです。
出典:DIAMOND online「せめて遺族の“最期の別れ”は気持ちよく――。
極限状態で遺体保護を続けたエンバーマーの素顔」
エンバーミングの由来と目的
エンバーミングの目的として、「故人を生前の状態に近づけ、心やすらかに見送れるようにすること」があります。
事故などで亡くなったり、長患いでお顔がやつれたりたりしてしまっている場合、生前の元気で生き生きとした姿でお見送りをしたいと考える人は多いかと思われます。
死に化粧でももちろんある程度は対応ができますが、ご遺体の損傷が激しい場合はこれだけでは対応できないこともあります。
海外においては「長く生前の姿をとどめておける」「ご遺体から感染症にかかるリスクを抑えられる」というメリットが取り上げられます。
ヨーロッパなどでは、特にこれが重要視されています(ただし、「血液を抜いている間に感染症にかかる可能性もあるのではないか」とする声もあります)。
もっとも、日本のように、火葬が前提となっている国ではこれらを目的としてエンバーミングを行うケースはそれほど多くはないかと思われます。
ただ、火葬までに時間がかかる場合は、もちろんこれを目的として行われることもあります。
- 「故人が火葬されるまで、つきっきりでいたい」
- 「添い寝をしてあげたい」
- 「冷たい体にはしたくない。ドライアイスは使いたくない」
と考える人にとっても、このエンバーミングは意味のあることだといえるでしょう。
また、
- 「日本に留学・仕事中に亡くなったが、祖国はアメリカ。ふるさとに帰るまでに時間がかかるから、ご遺体が傷まないか心配」
- 「沖縄に住んでいたが、故郷は北海道。葬儀は北海道で挙げたいし、できるだけ生前に近い姿で送りたい」
というケースにも、エンバーミングは有効です。
エンバーミングと湯灌、エンバーミングと死に化粧の違い
「エンバーミング」「湯灌(ゆかん)」「死に化粧」は、すべて死後に施されるものであり、ご遺体を美しい状態に保つための作業であるという点では共通しています。
しかしこれらは区別されるべきものです。
エンバーミングと湯灌の違い
湯灌は、亡くなった後の故人の身を清めるために行うものです。自宅のお風呂や専門のお風呂を使って故人を入浴させるものです。髪の毛も洗い上げます。
水を入れてからお湯を入れて温度を調節する「逆さ水」で作ったお湯の中で故人の体を清めます。
また、この湯灌の儀式には、髭剃りなどの作業も伴います。
エンバーミングは家族の立会をさせないのが基本ですが、湯灌の場合は家族が立ち会うこともあります。ただこれも絶対ではなく、スタッフだけで行う場合もあります。
湯灌もまた体を清めるために役立つ作業ではありますが、エンバーミングとは異なり、防腐処理は行いません。
また、遺体修復を前提とする作業ではないこと、ご遺体の状態によっては湯灌を頼むことができない場合などもあります。
エンバーミングと死に化粧の違い
死に化粧とは、旅立つ前にお顔などに化粧を施し、美しくする作業をいいます。どこまでをやってくれるかは業者によって異なりますが、清拭(せいしき)という「体を拭き清める工程」もここに含まれる場合もあります。
死に化粧は病院で行ってくれる場合もありますが、死に化粧を専門とする専門業者に頼むこともできます。病院で行う際は、医療器具の除去などを中心として行われることが多いかと思われます。
死に化粧を担当する業者に頼むと、死に化粧用に特化した化粧品を使って行ってくれる場合もあり、亡くなった後のお顔の状態を生前の状態に近づけることも可能です。
加えて、故人が生前愛用していた化粧道具を託せば、その化粧道具を使って化粧を施してくれるところもあります。仕上がりに希望がある(「若々しくしてほしい」「可愛らしくしてほしい」など)ならば、それも伝えるとよいでしょう。
なお、専門業者ではなくても、葬儀会社でも通常プランの一種としてこの「死に化粧」を組み込んでいる場合もあります。化粧というと女性だけのものと思われがちですが、土気色などに変色してしまったお顔を生前の状態に近づけるために、男性に対しても死に化粧を施す場合もあります。
なお、死に化粧は、「エンゼルメイク」「ラストメイク」などのように記される場合もあります。
エンバーミングとは異なり「防腐処理」は工程に含みません。
また、湯灌のときに必須となる「入浴」も清拭で代えられることがあります。特に湯灌やエンバーミングを希望しない場合はこの死に化粧のみで送られることもあります。
生前の美しいお顔を短期間保つだけならば、死に化粧だけで十分なこともあります。
エンバーミングを頼むには
エンバーミングは、日本ではまだ浸透しきってはいない技術です。そのため、エンバーミングを行える業者は限られています。エンバーミングは、技術だけでなく設備も必要なものですから、業者をきちんと選ぶことが重要です。
現在はエンバーミングを専門にしている業者もあるので、そこに打診してみるのもよいでしょう。その際には、利用する葬儀会社にも伝えておくようにします。また、「どこの会社を選べばいいかわからない」「自分で選ぶことは難しそう」という場合は、葬儀会社に相談してください。
少ないながらも、自社でエンバーミングを行えるとしている葬儀会社があります。また、自社ではサービスとして提供していなくても、お客様からの相談があればなんらかのアドバイスをするように努力する、という葬儀会社が大半であるかと思われます。
ちなみに、エンバーミングを行う会社の場合、多くのケースで「湯灌」「死に化粧」も担当することが可能です。
ただ、湯灌や死に化粧を行う業者では、「湯灌の専門業者であり、死に化粧までは行える。しかしエンバーミングは行えない」とする業者もありますし、「葬儀業者だが、業務の一環あるいはプラスアルファの料金で死に化粧までは担当できる。しかし、湯灌やエンバーミングまでは担当できない」としているところも多く見られます。
これに関しては一概に言い切ることができませんし、「業者によって違いがある」とまでしかいえません。
エンバーミングまでを希望しているのであれば、しっかりとそれを伝えたうえで、対応できる業者を選ばなければなりません。なお、現在は出張でのエンバーミングに対応している業者もあります。
一般的なエンバーミングの行程について
エンバーミングのやり方は、だいたい以下のような手順をとります。また、ここに遺体修復などの手順が差し挟まれることもあります。
- 傷の確認を行うとともに、殺菌処理などを行う
- 口の縫合などを行い、口を閉じさせる
- 血液を抜き取り、防腐液などを注入する
- 不要な水分を抜くためにご遺体をもみほぐす
- 体液を吸引する
- 内臓に防腐液を入れる
- 傷口を縫う
- 体を洗いあげ、乾かす
- 体から生じる液を留めるための処理を行う
- 故人の好きだった洋服、あるいはご家族が希望する服に着替えさせる
- ご家族の希望、あるいは自然に見えるような化粧をして、生前のお姿に近づける
死に化粧や湯灌に関しては、家族の立ち合いが許可あるいは推奨されます。しかしエンバーミングの場合は極めて特殊な処理であることから家族は立ち会えません。
メスを使った施術も必要となるため、ご家族が見るには衝撃が強い場合も多いというのも理由の一つだと考えられます。
エンバーミングと宗教の関係
日本には火葬の文化がありますが、アメリカなどでは火葬は馴染みのないものでした。これは、キリスト教の教義によるものだとされています。特にカトリック教会においては、「善き行いをした者は、最後の審判にときに復活する」と考えていました。
このため、火葬は宗教観にそぐわないものであるとし、ご遺体を長く保存できるエンバーミングが広く用いられていました。
ただ、このような宗教観の元に広がっていったエンバーミングですが、現在は少し状況が変わっていっています。日本に比べればまだ普及率は高く、また浸透している概念といえそうですが、1913年から1965年にかけて、「火葬は、宗教上否定されるべきものではない」という見解がカトリック教会から出されたのです。
チェコ・カトリック教会から出されたこの見解は、イギリスやフランスにも広がりました。そして、最終的に1965年にバチカンから正式にこの見解が出されたのです。
現在においても、日本に比べて国土が広いこともあるのかもしれませんが一部の州では「移動する距離によっては、エンバーミングは義務である」としています。ただ、年々エンバーミングを行う比率は減っていっているといわれています。
かつては宗教的な意味から行われていたエンバーミングは、現在では「政治的な意図」をもって行われることも出てきました。
指導者・統治者の威光を残す目的で行われることも多く、場合によっては「展示物」としてエンバーミングを施した指導者・統治者のご遺体が飾られることもあります。
日本におけるエンバーミングの施術率
納棺師の仕事などが取り上げられるようになった現在、「エンバーミング」についても関心を寄せる人も出てきました。
しかしながら、火葬が行われる日本においては、エンバーミングはまだまだ一般的な技術とはいえません。
正確な数字ではありませんが、エンバーミングの実施率は数パーセント程度だとされています。つまり、ほとんどの人はエンバーミングを施さない状態で旅立つことになるのです。
特に、火葬までの時間が短い状況ではエンバーミングを施さなくても死に化粧で十分対応できることもあるでしょう。
ただ、現在はエンバーミングを学ぶための学校などもできています。2012年の段階では全国に120人程度しかいないとされていたエンバーマーも、2019年現在はもっと増えているかもしれません。
エンバーミングを行うメリット・デメリット
エンバーミングを行うメリットとしては、
- 在りし日のお姿に近づけることができる
- 海外に故人をお連れするときでも、安心感が強い
- 夏場で、かつ火葬が遅くなってしまう場合でもご遺体が傷みにくい
- ドライアイスを使わないため、ご遺体の側で一緒に過ごしやすい
というメリットがあります。
特に、損傷の多いご遺体の場合は、エンバーミングは強い味方となるでしょう。
家族のなかでもとりわけ強いショックを受けるであろう人との対面の前に、ほかのご家族がご遺体の修復をお願いするケースもあります。
ただし、エンバーミングにもデメリットはあります。
エンバーミングを行う際は、ご遺体にメスを入れる必要が出てきます。
このため、これに抵抗感を覚える人もいるでしょう。故人が生前に臓器提供や献体を希望していた場合でも、ご遺族から「亡くなった後の体であっても、切られるのはかわいそうだ」と反対が出ることもあります。
「亡くなった人は痛みを感じないから」と言ったとしても、これは極めて感覚的な問題です。エンバーミングでも、同じように抵抗感を覚える人は当然いると思われます。
「生前の姿に近づけてお別れをしたい」という気持ちも、「亡くなった人をこれ以上傷つけたくない」という気持ちも、両方とも、ご家族の気持ちとしては理解できるものです。
また、エンバーミングは当然のことながら保険の対象外となります。費用は業者によっても異なりますが、20万円程度の出費は覚悟しなければなりません。
ちなみに、「エンバーミングをしなくても、湯灌などをすれば同等程度のお金がかかる」としているホームページもあります。
これはある意味正解なのですが、葬儀会社によっては「メイクやドライアイスは料金に含まれる」としているところもありますし、「そもそも湯灌は必要ない。清拭で十分」とされるケースもあります(あくまで個人的な体験談に基づくものではありますが、1年間の間に、1度も湯灌もエンバーミングも注文・打診されなかった、という葬儀会社もあります)。
このため、やはり、「エンバーミングには特別の料金がかかる」と考えるのが妥当だと思われます。
ご臨終から葬儀までの故人の扱いの流れ
エンバーミングを行う際の、ご臨終から葬儀までの流れを見ていきます。なお、ここでは分かりやすくするために、「エンバーミングのサービスを提供できる葬儀会社」を利用したと仮定します。
- ご臨終後、葬儀会社に連絡をする
- 病院に葬儀会社のスタッフがやってくる
- 打ち合わせ~ニーズの聞き出し~契約
- エンバーミング施設へ移動する
- エンバーミング処理を行う
- 故人あるいは遺族が希望した服装へのお着替え
- 死に化粧を施す
- 必要に応じて納棺を行う
- ご遺体を自宅もしくは式場にお連れする
ここまでが、エンバーミングを施す場合の一連の手順です。この後は通常の葬儀と同じやり方をとることになりますが、その手順についても簡単に紹介していきます。
また、ここでは仏教での葬儀を想定しています。故人をお連れする場所は自宅とし、通夜に臨むときに式場に移動するものとします。 - 自宅にお連れし、枕飾りなどを施す
- 枕経をあげる(現在は省略されることもある)
- 8で納棺をしていなかった場合はこの段階で納棺が行われることが多い
- 詳細な打ち合わせ
- 通夜に向けて、故人を葬儀会場にお連れする
- 通夜を行う
- ご遺体は通夜が終わった段階で、御遺族様控え室に移動されることもある
- 通夜振る舞い
通夜が終わると、待っているのは「葬式・告別式」です。特段の事情がない限り、葬式・告別式は通夜の翌日に行われます。 - 葬式・告別式の開始
- 出棺。霊柩車
(現在では洋型霊柩車が用いられることも多い)、バスなどに分かれて、ご遺族・ご親族・故人で火葬場に行く - 火葬場の炉の前で最後のお別れ。
「肉体をとどめている故人」との最後のお別れの場が設けられる - 炉に点火。
喪主が点火することもあるが、火葬場のスタッフが押すこともある - 火葬が終わるまで待つ。
待合室が設けられているので、そこで軽食などを取りながら待つのが一般的 - 火葬終了の案内があるので、収骨を行う
収骨後解散となるケースもないわけではありませんが、現在はその後に葬儀会場に戻ってきて繰り上げ法要などを行うかたちもよく見られます。 - 葬儀会場や法要会館に帰還
繰り上げ初七日法要を行う。この段階では、故人はお骨となっており、骨壺に納められている(骨壺はカバーで覆われている) - 繰り上げ精進落としの席が設けられる
- 繰り上げ精進落としが終われば解散
ご家族は、骨壺・遺影・位牌などを持って自宅に帰る
通夜以降の手順は葬儀会社やスケジュールによって多少異なりますが、基本的にはこの流れが取られます。
まとめ
エンバーミングとは、ご遺体に防腐処理を施し生前の姿に近い状態で保つ技術・施術を指す言葉です。日本は火葬の文化があるためそれほど重要視されませんが、
- スケジュールの都合で、火葬までに時間がかかる
- 国外の方あるいは遠方の方が亡くなられ、飛行機などでの移動を必要とし、また移動に時間がかかる
- ご遺体の損傷が激しい
などのケースの場合は、エンバーミングで対応することもあります。エンバーミングにおいては、多くの場合、「ご遺体の修復」もプラン内容に組み込まれるからです。
ドライアイスを必要としない処理ですから、冷たいご遺体にはならないというメリットもあります。加えて、死臭や腐臭も押さえられます。
エンバーミングは元々アメリカの南北戦争のときに大きく発展した技術だといわれています。
また、現在でこそ「火葬を行ったとしても、キリスト教の教義には反しない」とされていますが、かつてカトリックでは火葬はタブーだったとされていることもまた、海外でエンバーミングの技術・考え方が根付いた理由と考えられています。
昔から火葬の文化があった日本での施術率は、数パーセント程度にとどまっています。また、エンバーミングには20万円ほどの費用がかかるということもあり、日本ではなかなか普及しません。
エンバーミングは防腐処理を行うという一点において、「湯灌」と差別化されます。また、「死に化粧」の場合は湯灌とも異なり清拭(体を拭く)だけで入浴を伴わなくても構わないという違いがあります。
ただ、どの方法であっても、「ご遺体を生前の状態に近づけ、その人らしいお顔にするためにあるもの」という点は共通しています。
ちなみに、エンバーミングや湯灌は別料金となることが多いのですが、簡単な死に化粧までならば葬儀会社で行ってくれることもあります。
エンバーミングを頼む際は、専門業者に依頼するとよいでしょう。エンバーミングにはエンバーミング施設が必要であるからです。
特に、「湯灌はしているけれども、エンバーミングはできない」という業者もあるのでご注意を。なお、葬儀会社のなかには、エンバーミングサービスも提供できるとしているところもあります。
また、たとえ自社でエンバーミングサービスを提供していない葬儀会社であっても、喪家側が希望すれば、なんらかのアドバイスはくれるものと思われます。
東日本大震災のときにも、エンバーマーの方々が活躍しました。エンバーミングを行う際には体にメスを入れる必要があるためこれを嫌がる人ももちろんいますし、この考え方も否定されるものではありません。
しかしエンバーミングは、「その人らしいお別れ」「ご遺族にとって、できるだけ心やすらかなお別れ」を実現するために用いられるものです。特に、ご遺体の損傷が激しく、傷ついた体での見送りは避けたいと考えるご家族の心境に寄り添えるものです。
ライフドット推奨
後悔しないお墓のために今から準備してみませんか?
終活といっても、生前整理、葬儀、お墓の検討などさまざまです。
そのなかでも「お墓」は、一生に一度あるかないかの買い物ですね。
- 自分のライフスタイルに合ったベストなお墓はどういうものなのか知りたい
- お墓選びで複雑な手順を簡単に詳しく理解したい
- お墓選びで注意するべきポイントを詳しく知りたい
など、数々の不安を抱えている方が多いのではないでしょうか。
お墓の購入に関しては、初めての方が多いため、不安や疑問を持つことは仕方のないことでしょう。
しかし、お墓購入後に後悔することだけは避けたいですよね。
そのためにも複数の霊園・墓地を訪問して実際に話を聞き、しっかりと情報収集することをオススメします。
情報収集するために、まずは気になる霊園・墓地の資料請求をしてみましょう。